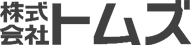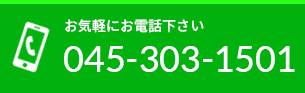Messege
― ご挨拶
株式会社トムズは1984年の創業以来、シロアリ・衛生害虫獣・不快な害虫・野外の毒虫・衣食住害虫などの駆除、防除を業務の柱とし、環境衛生および建築物全般に関するサービスの提供に努めております。
近年の環境問題は、外来生物の侵入増殖(アメリカカンザイシロアリ・アライグマ・タイワンリス・アルゼンチンアリ・セアカゴケグモ)や宿泊施設でのトコジラミの猛威、デング熱を媒介するヒトスジシマカ(2014年)など、深刻な問題が現実に迫ってきています。
私たちは環境問題、環境保護への取り組みとして、衣食住の安全・清潔・快適性、そして皆様の健康的な暮らしをサポートするために日々、技術の向上、防除施工や薬剤などに関する正しい知識を身につけるための学習・研修・研究に努めてまいります。

Work
― 主な施工実績 ―

箱根神社
徳善寺
三雲禅堂
観音禅寺
龍寶寺 鎌倉三雲禅堂 国立筑波大学 清来寺 国立東京工業大学
神奈川県立公文書館 よこはま動物園ズーラシア ララポート船橋(飲食店街) 他多数

Service
― 業務内容
シロアリ駆除・防除
害虫駆除・ネズミ駆除、防除・鳩飛来防止
床下環境改善
等 皆様の暮らしを守るお手伝いをさせていただいております。
株式会社トムズでは皆様の住環境や状況に応じて、シロアリ駆除・防除の薬剤を使い分けて駆除・防除処理を行っております。
動物、魚類などにも毒性が低く、確かな防蟻効果が長持ちするオプティガードシリーズ。自然界に存在する天然除虫菊エキスを使用した天然ピレトリンMCシリーズ等。住環境・周辺施設に応じ、効果の高い施術を行います。
Information
― お知らせ ―
-
- 2024年8月10日
アシナガバチ
スズメバチ科アシナガバチ亜科に属するハチの総称で日本には3属11種が生息している。
スズメバチ科だけあり、アシナガバチの生態はスズメバチに似ている。細身で小型の体型は攻撃力で劣るが、幼虫の餌に他の昆虫の肉を与えることなど共通点も多い。スズメバチ同様、ヤブガラ等の花に飛来することも多い。また、比較的低い乾燥した物陰や樹幹に巣を作る。20日ほどで幼虫は成虫になる。この蜂の巣は、蓮の実のような形につくられて100部屋を超える巣もある。性質はスズメバチに比べればおとなしく巣を強く刺激したり蜂を素手で触ったりしない限りはまず刺してはこない。毒はスズメバチに比べれば弱く、毒そのものによる死亡は稀であるが、アナフィラキシーショックにより死亡することもあるので、過去に刺されたことがある人は注意が必要である。
-
スズメバチ
ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科(Vespinae)に属するものの総称で、ハチの中でも比較的大型の種が多く、その性質は獰猛でスズメバチの刺害による死亡例は熊害や毒蛇の咬害によるそれを上回る。
日本にはスズメバチ属7種、クロスズメバチ属5種、ホオナガスズメバチ属4種の合計3属16種が生息する。スズメバチは、狩りバチの仲間から進化したと見られており、ドロバチやアシナガバチとともにスズメバチ科に属する。スズメバチ類は巣や縄張りに強い防衛行動をもつため、10m以内に近づくと警戒行動をとり接近者の周囲を飛び回る。また好戦的な性格であるため、警戒行動なく刺してくることもある。蜂の接近に驚いて騒いだり、はたき落そうとしたりすると、却って蜂が興奮して危険度が増す。また香水や制汗スプレー、色の濃い服もスズメバチを興奮させる恐れがあるので注意が必要である。
スズメバチ類は強力な毒を持つものが多い。他者への攻撃性も高くミツバチと違って一度刺しても自身が死ぬことはないため毒液が残っている限り何度でも刺してくる。これらの毒物質の多くは人を含む動物の免疫系や神経系の情報処理機構を攪乱しそれによって激しい痛みや免疫系の混乱による急性アレルギー反応(アナフィラキシーショック)などを引き起こす。
-
- 2024年7月1日
ゴキブリ(蜚蠊)
昆虫綱ゴキブリ目(Blattodea)のうちシロアリ以外のものの総称。シロアリは系統的にはゴキブリ目に含まれるが、「ゴキブリ」に含められることはなく、伝統的には別目をなす。なお、カマキリ目と合わせて網翅目(Dictyoptera)を置き、Blattodeaをその下のゴキブリ亜目とすることがあるが、その場合、ゴキブリとはゴキブリ亜目(のうちシロアリ以外)となる。長い触角、扁平な楕円形の体、発達した脚などを特徴とする。
熱帯地域を中心に世界に約4000種が生息し、そのうち日本産のものは8科約50種で、人家に侵入するゴキブリの種は約30種とされる。チャバネゴキブリ、イエゴキブリ、クロゴキブリ、ワモンゴキブリ、などは都市部の繁華街、民家、飲食店などで多くみられ、これらはいずれも外国から侵入したもので、その原産地は正確にはわかっていない。本州のみに分布するヤマトゴキブリは日本の固有種とされ、民家の台所などでよくみられる。これら家屋に侵入するものは、衛生害虫のなかでも不快さのみが強調され、不快害虫としてまとめられている。ただし、家屋害虫となるゴキブリの種類は全てのゴキブリのうち1%にも満たない。おもに森林中などに生息する。
-
- 2024年6月11日
イエシロアリ(学名:Coptotermes formosanus)
シロアリ目(等翅目)ミゾガシラシロアリ科に分類されるシロアリの1種で建築物の害虫として重視されるシロアリ。(別名、タイワンヒメシロアリ)大きさは有翅虫で7 ~ 8mm、働きアリで5 ~ 7mm、女王アリは大きいもので40mmに達する。
ヤマトシロアリに似るが、全体的に大きいく兵隊アリの頭部は卵円形で扁平、大顎は鋭く、弯曲している。有翅虫は頭部が褐色で胸腹部は黄褐色で大きいのに対して、ヤマトシロアリは全体に小型で黒っぽい、明確に判別できる他のシロアリと同様社会性昆虫で、集団をなし、枯れ木や朽木を食べる。その内部に巣を作る。特に湿った材を好み、巣は材の中にいたるところに掘られた巣穴と、材の外に続く巣穴に作られた、塊状の巣からなる。この巣は、湿ったところの地下に作られ、そこからあちこちの材へとトンネルを繋げ、大規模に食害する。一群を構成する個体数は、数万匹以上で最大で100万匹に達する。
-
アメリカカンザイシロアリ(学名:Incisitermes minor )
ヤマトシロアリやイエシロアリが土の中で生息するのに対しカンザイ(乾材)シロアリは木の中だけに生息する。
アメリカカンザイシロアリの有翅虫は、体長7~8mm、黄褐色。翅は暗褐色の半透明で群飛は、6~9月に小規模ずつ何回も発生し続けることが多いが、暖房している室内では羽アリが1年中発生する。主に昼間に飛翔し、走光性はない。
兵蟻は体長約10mmで、頭部は黄褐色で大きい。木材や家具に孔を開けて集団で巣を作り、内部を食い荒らす。ひとつの巣の個体数は少なく食害の進行は遅いが同じ部屋内に多数のコロニーが住み着き被害が広範囲に及ぶこともある。
侵入の初期には木粉がまとまって落ちているのが見られ、その周囲に羽が落ちてることもある。被害が進むと俵型の糞が散らばる。