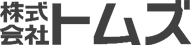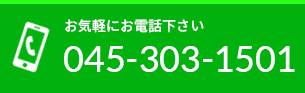Messege
― ご挨拶
株式会社トムズは、1984年の創業以来、シロアリ駆除や害虫・害獣の駆除・防除を中心に、建物の環境衛生サービスを提供してまいりました。
近年では、アメリカカンザイシロアリ、アライグマ、タイワンリス、アルゼンチンアリ、セアカゴケグモといった外来生物の増加や、宿泊施設でのトコジラミ被害、さらにはデング熱を媒介するヒトスジシマカの発生(2014年)など、新たな衛生リスクが深刻化しています。
私たちは、安心・安全な暮らしを守るために、最新の駆除技術や予防策を常に研究し、効果的な防除施工を提供。薬剤の安全性や環境負荷にも配慮しながら、適切な対策を提案いたします。
害虫・害獣の問題でお困りの方は、経験豊富なトムズにご相談ください。快適な住環境を守るために、最適なソリューションをご提供いたします。

Work
― 主な施工実績 ―

箱根神社
徳善寺
三雲禅堂
観音禅寺
龍寶寺 鎌倉三雲禅堂 国立筑波大学 清来寺 国立東京工業大学
神奈川県立公文書館 よこはま動物園ズーラシア ララポート船橋(飲食店街) 他多数

Service
― 業務内容
シロアリ駆除・防除
害虫駆除・ネズミ駆除、防除・鳩飛来防止
床下環境改善
等 皆様の暮らしを守るお手伝いをさせていただいております。
株式会社トムズでは皆様の住環境や状況に応じて、シロアリ駆除・防除の薬剤を使い分けて駆除・防除処理を行っております。
動物、魚類などにも毒性が低く、確かな防蟻効果が長持ちするオプティガードシリーズ。自然界に存在する天然除虫菊エキスを使用した天然ピレトリンMCシリーズ等。住環境・周辺施設に応じ、効果の高い施術を行います。
Information
― お知らせ ―
-
- 2026年1月10日
ドブネズミ(溝鼠、学名 Rattus norvegicus)
ネズミ目(齧歯類) ネズミ科 クマネズミ属 に属する大型のネズミ類の1種。世界各地に棲み、日本にもほぼ全域に棲息する。
頭胴長さ 186-280mm、尾長 149-220mm体重 約150-500g。ドブネズミの尾長は頭胴長より短い傾向がある(クマネズミの尻尾は頭胴長と同じか、それよりやや長い傾向がある)。
野外に棲息するアカネズミ、ハタネズミなどの「野ネズミ」に対して、人家やその周辺に棲息するネズミ類を、「家ネズミ」と呼び、日本のネズミ類のうちでこれに当たるものは、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミのほぼ3種に限られる。
水分を多く必要とするドブネズミは下水のまわりや河川、海岸、湖畔や湿地など、湿った土地を好み棲息する。水中に飛び込み、巧みに泳ぐ。ただし、人家から遠く離れた場所ではあまり見られない。市街地では、下水、台所の流し、ゴミ捨て場、地下街、食品倉庫など、 下水管の破れた部分や、コンクリートの下の隙間、公園、駅前、繁華街などの植え込みの地中、マンホール内、人家の床下、舗装道路上の物陰など、水分が十分に摂取でき、湿った場所を好む。クマネズミと違って、高いところに登るのはあまり得意ではないため、主に地表や建物の下層階で生活し、上層階には少ない。屋根裏を走り回るネズミは、たいていの場合クマネズミだが、ドブネズミは地下鉄の線路や地下街の通路に不意に現れ、見る人を驚かすことがある。
-
- 2026年1月9日
クマネズミ(熊鼠、学名:Rattus rattus)
ネズミ目(齧歯類) ネズミ科 クマネズミ属 に属する大型のネズミ類の1種。世界各地に棲み、日本にもほぼ全域に棲息する。
頭胴長146-240mm、尾長150-260mm、後足長22-40mm、体重150-200g。クマネズミの尾長は、頭胴長と同じか、それよりやや長い傾向がある(ドブネズミは、尾長が頭胴長よりやや短い傾向がある)。また、耳は比較的大きく、前に倒すと目が隠れる。これにより、ドブネズミ(耳が比較的小さく、前に倒しても目に達しない)と区別することができる。
クマネズミの多くは建物内に棲むが、畑の周辺や森林内などでも見られ、半樹上性生活をするものもいる。
建物内で暮らすクマネズミは、ビルや天井裏など、比較的乾燥した高いところに生活する。高さと幅が10cmくらいの空間を好む傾向があり、手足の肉球に滑り止めとなるヒダがあって登攀(とうはん)力にすぐれ、電線や水道管などもたくみに渡ることができる。
建物内は一年中温度が一定に保たれているため、冬でもさかんに繁殖し、主要都市を中心にクマネズミが増殖し続けている。また、他のネズミより警戒心が強く捕獲しにくいことや、殺鼠剤に耐性のある(肝臓の毒代謝能力の高い)ものが多く現れており、これも増加の一因となっている。
-
- 2025年8月29日
スズメバチ
ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科(Vespinae)に属するものの総称で、ハチの中でも比較的大型の種が多く、その性質は獰猛でスズメバチの刺害による死亡例は熊害や毒蛇の咬害によるそれを上回る。
日本にはスズメバチ属7種、クロスズメバチ属5種、ホオナガスズメバチ属4種の合計3属16種が生息する。スズメバチは、狩りバチの仲間から進化したと見られており、ドロバチやアシナガバチとともにスズメバチ科に属する。スズメバチ類は巣や縄張りに強い防衛行動をもつため、10m以内に近づくと警戒行動をとり接近者の周囲を飛び回る。また好戦的な性格であるため、警戒行動なく刺してくることもある。蜂の接近に驚いて騒いだり、はたき落そうとしたりすると、却って蜂が興奮して危険度が増す。また香水や制汗スプレー、色の濃い服もスズメバチを興奮させる恐れがあるので注意が必要である。
スズメバチ類は強力な毒を持つものが多い。他者への攻撃性も高くミツバチと違って一度刺しても自身が死ぬことはないため毒液が残っている限り何度でも刺してくる。これらの毒物質の多くは人を含む動物の免疫系や神経系の情報処理機構を攪乱しそれによって激しい痛みや免疫系の混乱による急性アレルギー反応(アナフィラキシーショック)などを引き起こす。
-
- 2025年7月29日
アシナガバチ
スズメバチ科アシナガバチ亜科に属するハチの総称で日本には3属11種が生息している。
スズメバチ科だけあり、アシナガバチの生態はスズメバチに似ている。細身で小型の体型は攻撃力で劣るが、幼虫の餌に他の昆虫の肉を与えることなど共通点も多い。スズメバチ同様、ヤブガラ等の花に飛来することも多い。また、比較的低い乾燥した物陰や樹幹に巣を作る。20日ほどで幼虫は成虫になる。この蜂の巣は、蓮の実のような形につくられて100部屋を超える巣もある。性質はスズメバチに比べればおとなしく巣を強く刺激したり蜂を素手で触ったりしない限りはまず刺してはこない。毒はスズメバチに比べれば弱く、毒そのものによる死亡は稀であるが、アナフィラキシーショックにより死亡することもあるので、過去に刺されたことがある人は注意が必要である。
-
- 2025年7月1日
ゴキブリ(蜚蠊)
昆虫綱ゴキブリ目(Blattodea)のうちシロアリ以外のものの総称。シロアリは系統的にはゴキブリ目に含まれるが、「ゴキブリ」に含められることはなく、伝統的には別目をなす。なお、カマキリ目と合わせて網翅目(Dictyoptera)を置き、Blattodeaをその下のゴキブリ亜目とすることがあるが、その場合、ゴキブリとはゴキブリ亜目(のうちシロアリ以外)となる。長い触角、扁平な楕円形の体、発達した脚などを特徴とする。
熱帯地域を中心に世界に約4000種が生息し、そのうち日本産のものは8科約50種で、人家に侵入するゴキブリの種は約30種とされる。チャバネゴキブリ、イエゴキブリ、クロゴキブリ、ワモンゴキブリ、などは都市部の繁華街、民家、飲食店などで多くみられ、これらはいずれも外国から侵入したもので、その原産地は正確にはわかっていない。本州のみに分布するヤマトゴキブリは日本の固有種とされ、民家の台所などでよくみられる。これら家屋に侵入するものは、衛生害虫のなかでも不快さのみが強調され、不快害虫としてまとめられている。ただし、家屋害虫となるゴキブリの種類は全てのゴキブリのうち1%にも満たない。おもに森林中などに生息する。